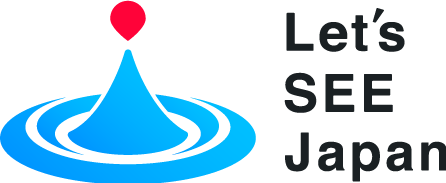なまはげとは、秋田県中部の男鹿半島で行われる民俗行事です。
毎年12月31日の晩になると男鹿半島のほぼ全域で、恐ろしい仮面と衣装を身に付けたなまはげたちが二人一組になって子どものいる家々を回り、「怠け者はいねが。泣く子はいねが」と大声で叫びながら室内に入ってきます。家の主はなまはげをもてなし、様々な問答をして、なまはげたちに帰ってもらいます。帰る際、なまはげたちはもてなされたお礼に次年の豊作を祈願してくれるのです。

なまはげは一連の行動により悪事を諫め、災厄を払い、豊作をもたらすと考えられています。実際、唸るような声を出すなまはげの来訪は、とくに子どもたちにとっては恐ろしいものであり、「悪いことをするとなまはげがやって来るぞ」と言われた子どもたちは、悪事をしないように気を付けるようになります。

【なまはげとは何者?】
寒い季節に炉端で火に当たってばかりいると、手や足に赤いまだらの模様が出てきませんか。男鹿半島があるこの地域では、これを「なもみ」と呼びます。これを剥ぐという意味の「なもみ剥ぎ」が変化して「なまはげ」になったと言われています。つまりなまはげとは、炉端で怠けてばかりいる人を戒める者という意味です。そのためなまはげは、「なもみ」をはぎ取るための大きな包丁と、はぎ取った「なもみ」を入れるための桶を持っているのです。
また、なまはげは、怠け者を戒めると同時に厄を払い、豊穣を祈ってもくれるので、神々の使者とも考えられています。そのためこの行事は、「来訪神:仮面・火葬の神々」としてユネスコの無形文化遺産にも登録されています。

【なまはげにはどこで会えるの?】

なまはげが家々を訪ねるのは毎年12月31日の夜です。その時間に地元の人の家にお邪魔していれば会えるのですが、さすがに難しいですよね。でもご安心を。男鹿市にあるなまはげ館に行けば、一年中いつでもなまはげに会うことができます。ここでは実際に使われた150枚を超える様々なデザインのなまはげの面を見ることができるほか、なまはげの衣装を着て記念写真を撮ることもできます。また、すぐ隣にある牡鹿真山伝承館では、曲家というこの地方の民家を利用し、実際のなまはげを体験することができます。恐ろしい唸り声をあげて家に入って来るなまはげは迫力満点。でも、乱暴そうに振る舞っていても、よく見るとその所作には作法があることに気付きます。これを見ると、なまはげという伝統文化の奥深さが伝わってきます。
なまはげ館に行ったら、次は真山神社にお参りをしましょう。ここはなまはげに縁の神社で、毎年二月の第二金・土・日には雪のなか柴灯(せど)祭が行われます。祭りでは、なまはげ踊りやなまはげ太鼓が披露されるほか、山から松明をもった本物のなまはげが降りてきて、境内を歩き回ります。夜の雪のなか松明をもって歩くなまはげの姿は幻想的ですらあります。
外見は恐ろしいのに、中身は神の使い。なまはげは極めてユニークな存在だと言えます。日本の冬を代表する伝統行事でもあるので、この地域を訪れた際は是非ともなまはげを体験してください。